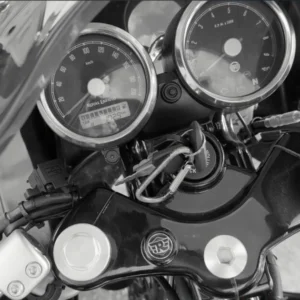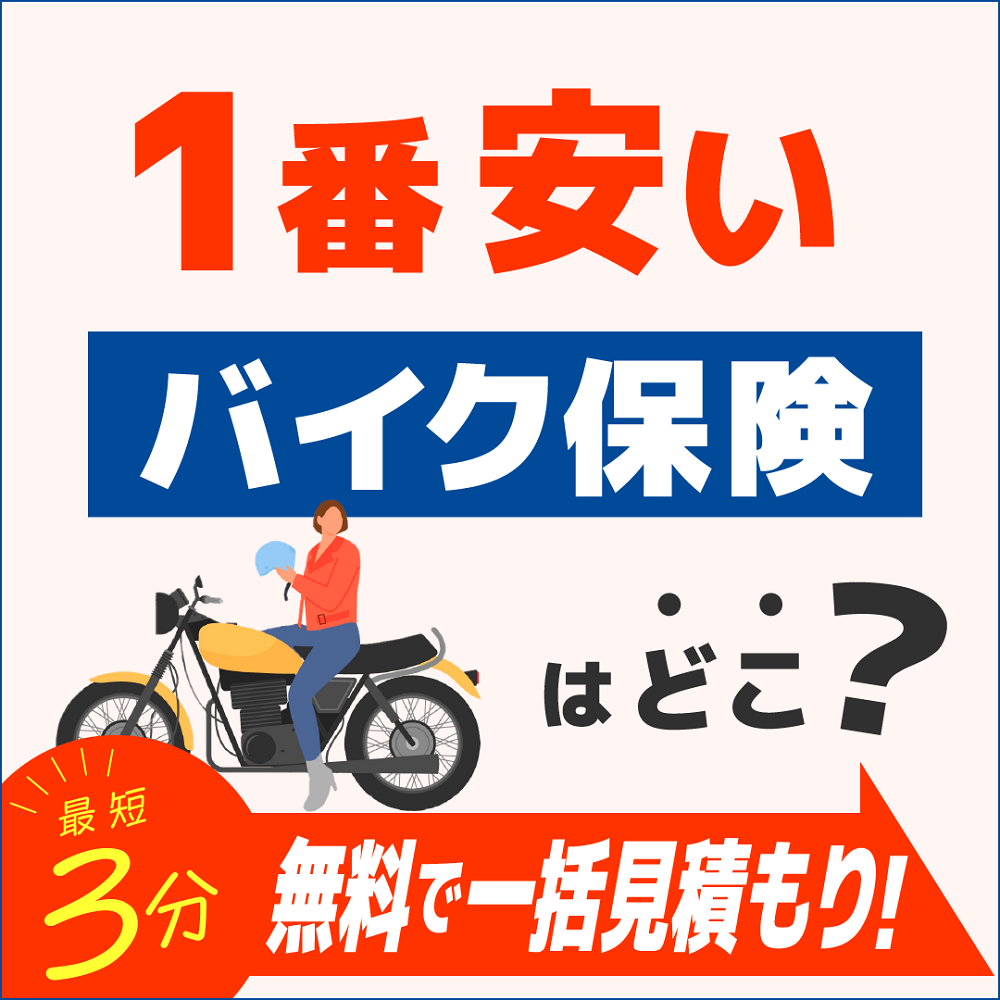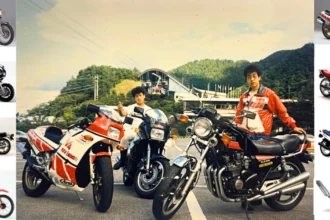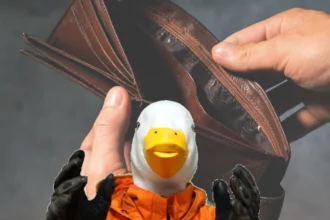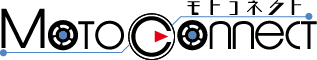「軽二輪って125cc?小型二輪とはまた違うの?」
「軽車両って…バイクも含まれる?」
バイクに乗り始めたばかりの方や、試験勉強中の方が必ず一度は悩む“バイクの呼び方問題”。その原因は、「道路交通法」と「道路運送車両法」で区分や呼び名が異なるからです。
例えば125ccのバイクは「原付二種」とも「軽二輪」とも呼ばれ、250ccを超えると「小型二輪」と分類されます。でも、これは法律ごとに基準が違うため。
さらに「軽車両」という言葉も混乱の元で、バイクや軽自動車とはまったくの別物。
この記事では、こうしたややこしいバイクの区分や呼び名を、法律ベースで整理し、初心者でもスッキリ理解できるように解説します。
ややこしい呼び方を一発解決!バイク区分の早見表
| 排気量 | 道路交通法 | 道路運送車両法 | 通称・呼び名 | 必要な免許 |
|---|---|---|---|---|
| ~50cc | 原動機付自転車 | 原付一種 | 原付一種 | 原付免許または 普通自動車免許 |
| 51cc~125cc | 普通自動二輪車 | 原付二種 | 原付二種 | 普通自動二輪免許 (小型限定) |
| 126cc~250cc | 普通自動二輪車 | 軽二輪 | 中型バイク (中免) | 普通自動二輪免許 |
| 251cc~400cc | 普通自動二輪車 | 小型二輪 | 中型バイク (中免) | 普通自動二輪免許 |
| 401cc~ | 大型自動二輪車 | 小型二輪 | 大型バイク | 大型自動二輪免許 |
まずはバイク区分の全体像を一覧で把握しましょう。バイクの呼び方は、排気量や法律の違い、免許制度の歴史的経緯によって複雑に分かれていますが、表で見ることで混乱を防ぎやすくなります。
※原付二種(51cc〜125cc)には「普通自動二輪(小型限定)」以上の免許が必要です。
※126cc〜400ccは一般的に「中免」と呼ばれますが、正式には「普通自動二輪免許」となります。
【補足:中免・小型限定免許の通称と背景】
「中免」とは、排気量400cc以下のバイクを運転できる「普通自動二輪免許」の俗称です。1970年代半ばから1995年ごろまで使用されていた免許区分「中型限定自動二輪免許」に由来します。また、「小型限定自動二輪免許」は1972年に導入され、125cc以下のバイクに限定して運転可能。1996年の法改正により、現在の「普通自動二輪免許(小型限定)」という名称に変更されました。
こうした表と解説で整理しておくと、法律や免許制度による呼び名の違いや通称を正確に理解できます。混乱しやすい部分も、排気量・区分・免許制度の成り立ちから読み解くことで、よりスッキリ把握できます。
新基準原付とは?

新基準原付とは、2025年4月1日施行の法改正により新たに導入された、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW(5.4ps)以下の二輪車を対象とする車両区分です。従来の原付一種と同じ交通ルールが適用されます。
| 区分 | 排気量・出力基準 | 必要免許 | 法定速度 | 二段階右折 | 二人乗り | ナンバー色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原付一種 | 50cc以下 | 原付免許・普通免許 | 30km/h | 必要 | 不可 | 白 |
| 新基準原付 | 125cc以下・4.0kW以下 | 原付免許・普通免許 | 30km/h | 必要 | 不可 | 白 |
| 原付二種 | 50cc超~125cc以下(出力制限なし) | 小型限定普通二輪免許以上 | 60km/h | 不要 | 可能 | 黄/ピンク |
新基準原付は、「125ccバイクがすべて原付免許で乗れる」わけではありません。最高出力が4.0kWを超える125ccバイク(従来の原付二種)は、引き続き小型限定普通二輪免許以上が必要です。
新基準原付は性能が抑えられているため、従来の原付一種と同じ交通ルールが適用されます。最高速度や二段階右折、二人乗り禁止などに注意が必要。
ナンバープレートや税額も原付一種と同じ扱いとなるので注意が必要です。
そもそも法律が違う!道交法と車両法の違いとは?

道路交通法と道路運送車両法は、どちらも自動車やバイクなどの車両に関する重要な法律ですが、目的と規制内容が大きく異なります。
道路交通法は「交通の安全と円滑」を目的とし、道路上での車両や歩行者のルール(信号、標識、運転免許、交通違反など)を定める法律です。
一方、道路運送車両法は「車両そのものの安全性や登録・保安基準」を定め、車両の設計・製造・整備・検査・登録など技術的・管理的な基準を規定しています。
これらの目的の違いによって、バイクの区分や呼び名も変わるため混乱が生まれます。
【例】125ccのバイク
- 道交法 → 普通自動二輪車
- 車両法 → 原付二種
と扱いが異なり、さらに2025年以降は新基準原付まで登場し、より複雑になっています。
ライダーが「どのバイクがどの免許で運転できるのか」「どの手続きや検査が必要なのか」といった点で混乱しやすく、購入や運用時には注意が必要です。
軽車両とは?バイクと混同してはいけない理由

軽車両とは、「原則として原動機を持たない車両」を指します。代表例は自転車、リヤカー、人力車、馬車などです。
軽車両の定義
- 道路交通法では「自転車や荷車など、人や動物の力で動かす車両。」と定められている。
- 道路運送車両法でも「人力や畜力で陸上を移動させるための用具」と規定。
- バイク(原動機付自転車や自動二輪車)は、原動機(エンジン)を持つため軽車両ではない。
- 軽自動車は、「軽」という言葉がついていても軽車両ではなく、あくまで「自動車」。
「軽車両」「軽二輪」「軽自動車」「原動機付自転車」など、似たような名称が多いため誤解が生じやすいですが、原動機(エンジン)の有無が最大の違いです。
軽車両は「エンジンなし」の車両(自転車など)を指し、バイクや軽自動車は含まれません。標識や交通ルールの理解を誤ると重大な交通事故にもつながるため、名称の違いと定義を正しく覚えておくことが重要です。
まとめ|ややこしさの正体は「法律の目的の違い」だった
バイクの区分や呼び方がややこしいのは、「道路交通法」と「道路運送車両法」という、異なる目的の法律が存在するからです。特に新基準原付の登場で、名称やルールがますます複雑になりました。
しかし、こうした違いの背景にある「法律の目的」に注目すれば、なぜ呼び方が複数あるのか、どうして条件が違うのかが見えてきます。
バイクに乗る方が正しく安全に楽しむためには、単なる名称の暗記ではなく、「何のための区分なのか?」という本質を理解することがカギです。
混乱しやすいバイク区分も、この記事の内容を参考にすれば、きっとすっきり整理できるはず。安全で楽しいバイクライフを送るために、ぜひ正しい知識を身につけましょう。
関連記事:
投稿者プロフィール
-
【✨ライダーを子どもたちの憧れに✨】
Mister Clean こと えもです!🏍️💨
ロイヤルエンフィールドのカフェレーサー「コンチネンタルGT650」とともに、九州を中心としたツーリングスポット、バイクの魅力、ライダーのライフスタイルを発信しています!
最新の投稿
カスタム2026年1月4日【2026年最新版】バイクの振動対策 5選!手や足痺れを劇的に改善する方法
コラム2025年12月31日【2025年バイク業界総決算】今年のバイク界はどう変わった?【話題のニュース10選】
お役立ち2025年11月27日【2025年冬最新版】足元ぽかぽか!冬におすすめバイクシューズ【5選+α】
メンテナンス2025年11月24日【保存版】バッテリー上がり防止!リチウムバッテリーの選び方&おすすめモデルまとめ